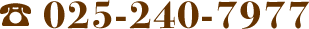No.3) 薬の位置付けは? (後篇)
「先週出してもらった薬で良くなりました。先生の(処方の)おかげです」
このような言葉を患者さんから頂くと、治療者として嬉しく感じないわけはない。
一方で、「ちょっと待てよ。本当にその薬のおかげで良くなったの?」と疑問に感じるケースも少なからずある。
このような疑問を抱く根拠として、「この薬(特に抗うつ薬)はそんなに早く効くものではない」、「こんな少量でそれほど劇的に改善するとは考えにくい」、「単なるプラセボ効果ではないのか?」、等々が挙げられる。
「結果オーライで良いのではないか」と考え、「良かったですねえ。では、同じ処方で続けましょう」としたくなるところではある。そうするのが一番楽ではあるし、「おかしいな」とは思いつつも、その誘惑を振り払うのは容易なことではない。何よりも患者さん本人が「この処方で良い」と言っているのに、敢えて処方を変えようとすると、怪訝な顔をなさる患者さんも少なくない。
ここで安易に同じ処方で続けると、次の診察日には掌を返したように、
「前(初診時)より悪くなった」、「薬が効かなくなった」と、「悪化」や「再発」を訴える患者さんが少なからずいる。待ち切れずに、予約日前に受診される方も珍しくはない。
前回の「良くなった」は一体何だったのか?
精神科医療は薬(薬物療法)だけで解決を図ることは難しい。「休養」、「環境調整」、「薬物療法」、「精神療法」、等々の「合わせ技」と考えた方が良い。
「仕事を休養して治療に専念する」ことにより、仕事上の疲労を軽減したり、職場の人間関係の悩みからも距離を置くことができる。これだけでも治療の面では有益である。
治療の面で有利な環境を整えることも重要である。人間関係の悩みも職場だけとは限らない。「嫁姑問題が解決した」、「円満に?離婚できた」、「ニートで引き籠りだった息子が就職できた」、「パワハラ上司が転勤になった」、等々、これだけで症状が改善することは珍しくはない。逆にこれらの問題を抱えたままでは、薬物療法効果はあまり期待できない。
治療が成功した結果をイメージすることも必須である。状態に応じて治療(方針)を修正する柔軟性も必要だが、目標が不鮮明では、治療も一貫性を欠いたものとなる。「何をどのように改善させるのか」、「その薬は何を意図して処方したのか」ぐらいは説明できる必要がある。精神科医療に限ったことではないが、患者さんの日常生活、経歴、人間関係、等々を把握し、大局観に立って、「理に適った医療」を行うことが求められていると考える。
奈良心療クリニック院長 奈良 康
(2014年09月28日更新)
診療日時
- 診療科/
- 心療内科、精神科
- 診療時間/
- 9:00〜13:00(受付8:30〜12:30)、
15:00〜18:00(受付14:30〜17:30) - 休診日/
- 木曜午後、土曜午後、日曜・祝日
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日/祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 15:00〜18:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
当院は予約優先で診療しております。
インターネット予約をご利用頂き、もしご希望時間帯に予約が取れない場合は、
電話でお問い合わせ下さりますようお願いします。